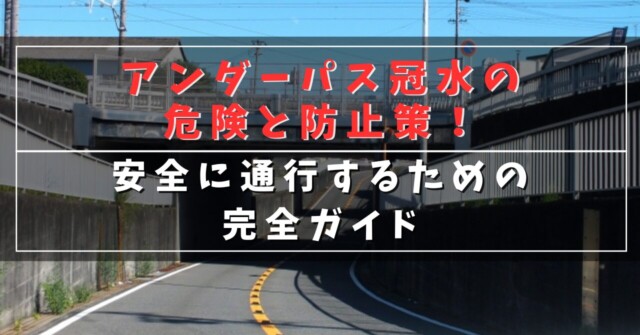アンダーパスは道路や鉄道の下をくぐるための構造で、渋滞緩和や交通の流れをスムーズにする役割を担っています。
しかし、その構造上どうしても地形が低くなるため、大雨の際には水がたまりやすく、冠水による事故が毎年のように発生しています。
実際、わずか数分の豪雨で通行可能だった道が水没し、車両が動けなくなるケースも少なくありません。
冠水したアンダーパスに進入すると、自分や同乗者の命を危険にさらすことになります。
本記事では、アンダーパス冠水の危険性と、防止・回避のために日常からできる対策を詳しく紹介します。
アンダーパス冠水が危険な理由

低地特有の水の集中
アンダーパスは周囲より低い位置に設計されるため、雨が降ると自然に水が流れ込む構造になっています。
特に周囲が舗装されている都市部では、雨水が地下に浸透しにくく、短時間で大量の水が集まります。
排水設備の限界
多くのアンダーパスには排水ポンプや側溝が設けられていますが、ゲリラ豪雨のような短時間集中豪雨では処理能力を超える水量となります。
排水ポンプは電源が必要なため、停電や機械故障が起きると機能しないこともあります。
見た目では水深が分からない
冠水したアンダーパスは、外見からでは水深を正確に判断できません。
浅く見えても30cm以上あることがあり、この深さでも多くの乗用車は走行不能になります。
特に夜間や視界が悪いときは、水面の反射で深さが錯覚されやすくなります。
急激な水位上昇
ゲリラ豪雨や上流からの排水によって、数分で膝の高さを超える水位になる場合があります。
このため、進入時は浅かった水が、出口に着く頃には脱出不可能な深さになっている危険があります。
アンダーパス冠水を避けるための行動と防止策
アンダーパス冠水を回避するためには、事前の情報収集と状況判断が欠かせません。
まず、大雨警報や注意報が発令されているときは、自治体や道路管理者の公式サイト、交通情報アプリ、道路情報板などを活用し、予定しているルートに冠水の恐れがないか確認しましょう。
近年では、Googleマップの経路情報にも「通行止め」表示が出ることがあり、こうしたツールを使えば外出前に危険なエリアを避けられます。
交通情報アプリに関しては、後ほどベスト3という形でご紹介します。
走行中は、アンダーパスの入り口に設置されている「冠水注意」の標識や水位表示ポールにも注意を払いましょう。
色分けや数値で水深が示されている場合は、たとえわずかに水が達している程度でも進入を控えることが重要です。
センサー式の遮断機が設置されている場合、バーが下がっていれば必ず迂回してください。
また、大雨や豪雨が予想される日は、通勤・通学ルートや外出経路を事前に見直し、高架道路や橋など冠水しにくい道を選びます。
カーナビやスマホアプリに複数のルートを登録しておくと、緊急時でも迷わず安全な道を選択できます。
さらに、見た目が浅い水たまりでも油断は禁物です。
水深20センチ程度でも車種によっては吸気口から水が入り、エンジンが停止する危険があります。
加えて水圧が高まるとドアが開かなくなる場合もあり、少しの水たまりのように見えても進入は避けるべきです。
冠水路進入時のEV・ハイブリッド・ガソリン車の違いは、JAFの動画が参考になるかと思います。
万一、走行中に冠水箇所で立ち往生してしまった場合は、直ちにエンジンを切り、シートベルトを外してドアまたは窓から脱出してください。
窓が開かない場合は、レスキューハンマーを使うと良いでしょう。
水位がドアの半分を超えると水圧で開かなくなるため、ためらわず早めに行動することが命を守る鍵になります。
冠水時に役立つアプリベスト3
アンダーパスの冠水は、事前の情報確認が何より重要です。
ここでは、大雨や冠水時の経路選択に役立つアプリを3つ厳選して紹介します。
車移動が多い方にも、公共交通機関を使う方にも対応できる内容です。
1. Yahoo!カーナビ(車利用が多い方に最適)
日本国内の道路交通情報に強く、JARTIC(日本道路交通情報センター)のデータを活用しているため精度が高いのが特徴です。
冠水や通行止め情報が反映されるのも早く、走行中には音声で警告してくれるため見落としを防げます。
完全無料で広告も少なく、日常的に車を運転する方には必須のアプリです。
2. Google マップ(幅広い移動手段に対応)
車だけでなく、徒歩や公共交通機関にも対応できる汎用性の高さが魅力です。
災害や大雨発生時には通行止めや渋滞情報を地図上で確認でき、迂回ルートを自動で提案してくれます。
旅行や出張先でも使えるため、日常から緊急時まで幅広く活躍します。
3. 特務機関NERV防災アプリ(防災意識を高めたい方に)
気象庁や自治体の公式データを基に、豪雨や洪水、避難情報などをリアルタイムで通知してくれます。
雨量や警報発令状況をいち早く知ることができるため、「今日はアンダーパスを避けたほうがいい」といった判断が早めにできます。
Google マップやYahoo!カーナビと組み合わせることで、より安全性が高まります。
これらのアプリは、それぞれ得意分野が異なります。
普段の移動スタイルや使い方に応じて使い分けるのが理想です。
車移動が多い方はYahoo!カーナビを、徒歩や公共交通機関も使う方はGoogle マップを、防災情報を常に把握したい方は特務機関NERV防災アプリを組み合わせると効果的です。
冠水による実際の事故事例
過去には、梅雨や台風シーズンに多くの水没事故が発生しています。
ある地方都市では、わずか10分間の豪雨でアンダーパスが冠水し、進入した車が途中で停止。
その直後、さらに水位が上昇して車内に水が流入し、運転手が車から出られなくなった事例が報道されました。
この事故は、救助隊の迅速な対応により命は助かりましたが、車は全損扱いになりました。
また、2020年の記録的豪雨では、冠水中のアンダーパスにトラックが進入し、途中でエンジンが停止。
周囲にいた人々の通報で救助されましたが、運転手は「浅いと思った」と証言しており、見た目と実際の水深の差が事故の一因だったことがわかります。
Q&A
Q1. SUVやトラックなら冠水を通行できる?
A. 車高が高くても、電気系統や吸気口が水没すればエンジン停止や感電の危険があります。
安全のため進入は避けるべきです。
Q2. 冠水の深さを見極める方法はある?
A. 水位ポールや標識で確認するのが確実です。
感覚や経験だけに頼るのは危険です。
Q3. 車両保険で水没はカバーされる?
A. 一般型またはエコノミー+水災特約が付いていれば補償対象となる場合があります。
Q4. 夜間はなぜ危険性が増すの?
A. 水面の反射や街灯の光で水深が錯覚されやすく、気づかず進入してしまう事故が多発します。
まとめ|危険を避ける一番の方法は「近づかない」
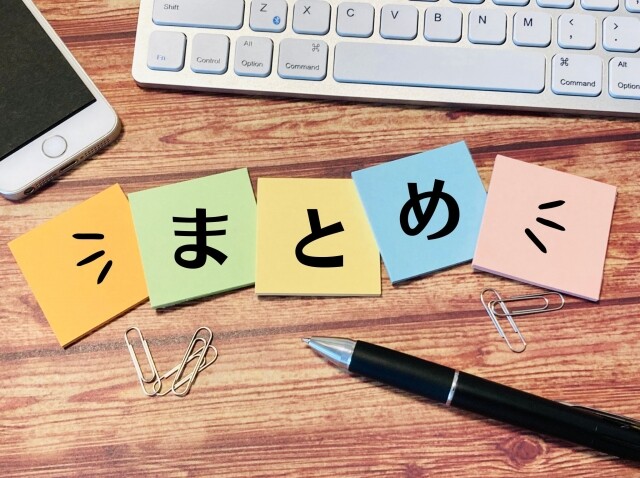
アンダーパス冠水は、短時間で命を脅かす状況を作り出します。
見た目では水深が浅く見えても、実際は走行不能になる深さに達している場合があります。
最も確実な防止策は、冠水の可能性があるときには進入しないことです。
事前の情報収集、ルート選択、標識の確認を徹底し、危険な場所に近づかない習慣を身につけましょう。
命を守るための判断は、いつも早めに行うことが大切です。