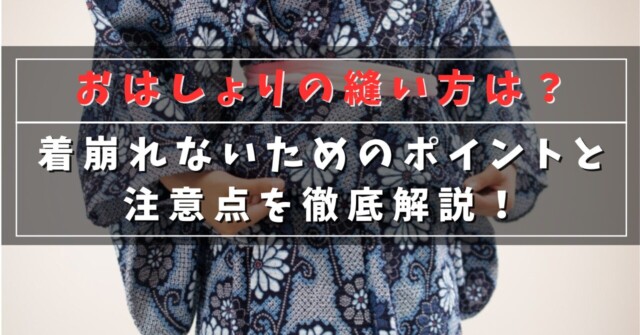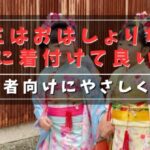浴衣を着る時、おはしょりがくしゃくしゃだと、どうしてもだらしなく見えてしまいます。
さらに着崩れの原因になってしまうので、何とかしたいもの。
おはしょりが綺麗に出来ていれば、全体がピシッと見えるものです。
それには着付けを上手にしないといけません。
そこであらかじめおはしょりを胴上げと同じように縫い付けることで、着崩れを防止することが出来ます。
この記事では、おはしょりの縫い方を解説し、着崩れないポイントまでお伝えします。
では早速みていきましょう。
おはしょりの縫い方は大人の場合はどうすればいい?

おはしょりの縫い方は、大人の場合も子供の「腰上げ」と同じようなやり方で縫います。
腰上げとは子供の着物の裾が長い時に、裾を折り返して縫うのではなく腰の部分をたくし上げて縫うお直しの事です。
浴衣を縫うなんてちょっと勇気がいるかもしれません。
でも縫った部分は帯で隠れるので、少しくらい縫い目が粗くても大丈夫です。
それに手縫いだとすぐにほどけるので、失敗してもやり直しが楽ですよ。
具体的な腰上げの方法は次の通りです。
- 腰上げする寸法を測る(腰上げ寸法=身丈-首から足首のくるぶしまでの長さ)
- 上げ山位置を決める
- 身丈の一番上からおはしょりの一番下までの長さを決める(おはしょりの一番下が上げ山になる)※実際に浴衣を羽織って位置を確かめると良いですよ
- 上げ山をつまみ、上げ山線から腰上げ寸法の半分の長さのところでまち針を打つ
- まち針部分を一直線に縫う
- 縫い方は二目落とし( なみ縫いなら糸は二本取りにする )※ミシンではなく手で縫います
- 上前( 左前 )の衿端は飛び出てしまうので中に折りこむ
画像で見ると分かりやすいので、こちらを参考にしてみて下さい。
説明の中に着物の部分名称が出てくるのでこちらも参考にどうぞ。
子供の場合は腰上げをしてもまだ長いので、さらにおはしょりを長く取って着付ける事があります。
腰上げと同時に「肩上げ」と言って袖も短く縫う事も多いです。
子供の浴衣姿は「腰上げ」「肩上げ」「長いおはしょり」が通常です。
大人の場合、本来ならおはしょりを作って着付けるのが通常です。
しかし、着物をまだ普段着として着ていた時代には、おはしょりを縫って着ていた事もあったそうです。
普段着だからこその生活の知恵だったのかもしれませんね。
浴衣は礼服や訪問着よりも気軽に着られる着物なので、簡単が一番です。
特に親子で浴衣を着る時は、サッと着て早く出かけたいですよね。
浴衣のおはしょりの縫い方のポイント
浴衣のおはしょりの縫い方のポイントは「付けひも」を付ける事です。
腰上げをしても、腰ひもは必要です。
その腰ひもを縫い付けてしまおう、という工夫なのです。
通常付けひもは、子供用の浴衣に付いているものですが、大人の浴衣にも付ければ着付けの時短になり、しかも、着崩れ防止にもなり一石二鳥です。
おはしょりの役割と課題
実は、おはしょりには浴衣の丈を調節するだけでなく、着崩れ防止の役割があります。
浴衣を腰の部分で段に折って腰ひもを結ぶと、その摩擦で浴衣がずれにくくなるのです。
ところが、腰上げをした浴衣は一枚の布を重ねただけの状態。
腰ひもで結んだだけではどうしてもずれてしまい、着崩れの原因になります。
そこで、腰ひもを縫い付けておけば、ずれる事なく安定し着崩れも防げるのです。
付けひもを付けるメリット
浴衣に付けひもを縫い付けておくと、腰ひもを別に使わなくても前合わせを簡単に固定できるため、初心者やお子さんでも着崩れしにくくなります。
特に子ども浴衣や自分で着るときにおすすめです。
それでは、浴衣の付けひもの付け方をご説明します。
浴衣の付けひもの付け方
- 腰ひもを半分に切る
市販の腰ひもを一本用意し、半分に切って二本に分けます。
- 腰上げした縫い目の両衿端(えりばた)に縫い付けます。
※襟端とは、衣服の首周りの部分、または首の後ろの部分(首筋)を指します。
実際に腰上げした浴衣を羽織り、腰ひもを結ぶ高さを確かめながら位置を決めると安心です。
- しっかりと縫い付ける
付けひもは結んだときに強く引っ張られるため、丈夫に縫うことが大切です。
四角の中に「ばってん」を描くように縫うと強度が増し、長く使えます。
結び方
浴衣を羽織ったら、右身頃を体に合わせ、左身頃をかぶせます。
内側と外側の付けひもをそれぞれ背中側で交差して軽く結び、その上から伊達締めや帯をします。
コチラの動画が参考になるかと思います。
動画では着物の場合の紹介ですが、浴衣にも同じ方法で応用できます。
ぜひ、参考にしながらやってみてくださいね。
まとめ:おはしょりは縫い方次第で着崩れ知らず!
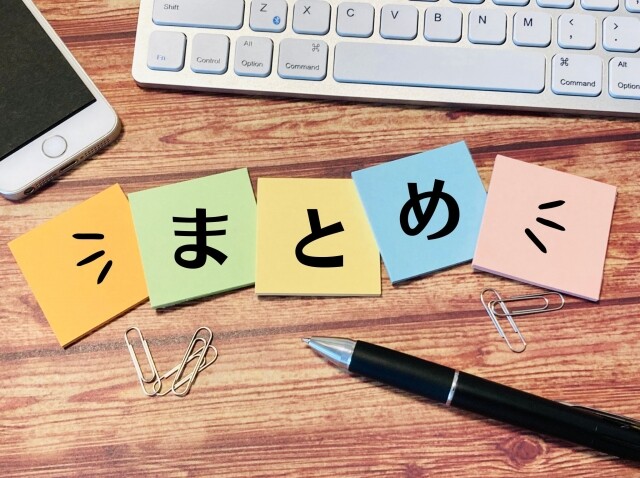
まとめると、
- おはしょりの縫い方は大人の場合も、子供の「 腰上げ 」と同じやり方で縫う
- 腰上げの手順
1.腰上げする寸法を測る
2.上げ山位置を決める
3.上げ山をつまみ、上げ山線から腰上げ寸法の半分の長さのところでまち針を打つ
4.まち針部分を一直線に縫う
5.上前( 左前 )の衿端は飛び出てしまうので中に折りこむ
- 腰上げは手縫いする
- 浴衣のおはしょりの縫い方のポイントは「付けひも」を付けること
- 付けひもの手順
1.腰ひもを半分に切る
2.腰上げした縫い目の両衿端(えりばた)に縫い付けます。
3.しっかりと縫い付ける
浴衣を着る時の一番の難関と言えば、おはしょりをきれいに出す事です。
おはしょりさえ綺麗に出来たら、浴衣はもっときれいに。
もしかすると、浴衣だけでなく着物を着る機会がもっと増えるかもしれませんね。
【参考】
⇒七五三はおはしょりなしで子供に着付けて良いの?初心者向けにやさしく解説
⇒着物のおはしょりとは?どの部分をどう作るか初心者向けに完全解説
⇒浴衣のおはしょりが長い時の処理方法!子供にきれいに着付けるコツ