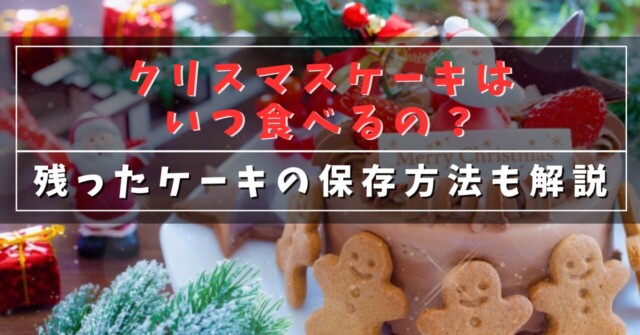クリスマスといえば、やっぱり欠かせないのが「クリスマスケーキ」。
でも、「24日に食べるの?」「25日?」「どっちが正しいの?」と迷う方も多いはずです。
実は、クリスマスケーキを食べるタイミングにはタイミングには“正解”があります。
また、食べきれなくて残ったケーキをおいしく保存するコツもあります。
この記事では、
- クリスマスケーキを食べる正しいタイミング
- 残ったケーキの保存方法
- 日本でケーキを食べるようになった理由
- 海外との文化の違い
を分かりやすく紹介します。
最後まで読めば、今年のクリスマスをもっと楽しめること間違いなしです。
クリスマスケーキを食べるタイミング

クリスマスケーキを食べるタイミングって、実は意外と悩むもの。
24日のイブに食べるのか、25日の本祭に食べるのか人によってバラバラですよね。
実は、クリスマスケーキを食べる“本来のタイミング”は12月24日の日没から25日の日没までの間なんです。
その間にパーティーを開いた時にケーキをケーキを食べればOK!
つまり、24日の夜でも、25日の昼でも大丈夫なんです。
この期間が「クリスマス」とされているため、どの時間に食べても間違いではありません。
家族が集まれる時間や、みんなでお祝いできるタイミングに合わせて楽しみましょう。
とはいえ、多くの家庭では24日の夜に食べるケースが多いですよね。
実はそれにはちゃんと理由があります。
「クリスマスイブは前夜祭」だと思われがちですが、実はそうではないんです。
「ちょっと何言ってるか分からない」という方のために、この点については次の章で詳しくお話ししますね。
クリスマスイブは前夜祭ではなかった!
日本では「イブ=前夜祭」と思っている人が多いですが、実は少し違います。
「イブ(Eve)」という言葉は、もともと「evening(夜)」を意味する古い英語です。
つまり、「クリスマスイブ」は“クリスマスの夜”そのものを表しているんです。
さらに、昔のヨーロッパではユダヤ暦という暦が使われており、日付の変わり目は午前0時ではなく「日没」でした。
そのため、12月24日の日没の時点で、すでに12月25日(クリスマス)が始まるという考え方になります。
このため、24日の夜にお祝いをするのは「前夜祭」ではなく「クリスマス当日」というわけなんです。
つまり、イブの夜にケーキを食べることは、むしろ“正しい過ごし方”だったんですね。
現代の日本では宗教的な意味合いはほとんどなくなっていますが、この文化が受け継がれた結果、「24日の夜=ケーキを食べる日」という習慣が自然に定着したのです。
食べきれなくて余ったケーキの保存方法
楽しい時間が過ぎたあと、ケーキが少し残ってしまうことってありますよね。
せっかくのクリスマスケーキ、美味しい状態で翌日も楽しみたいものです。
ここでは、おいしさを保つ保存方法を紹介します。
冷蔵庫で保存する場合
余ったケーキは冷蔵庫で保存できますが、そのまま箱に入れてしまうのはNG。
箱が湿気を吸ってしまい、ケーキの水分が抜けてパサパサになってしまいます。
- ケーキを皿に移す
- ラップをふんわりかける
- 匂い移りを防ぐためにタッパーなどの密閉容器に入れる
これで1〜2日は美味しく食べられます。
ただし、生クリームやフルーツを使っているケーキは劣化が早いため、翌日中に食べきるのが理想です。
冷凍保存も可能?
食べきれない場合は冷凍保存もOKです。
一切れずつラップで包み、ジッパー付き保存袋に入れて冷凍すれば、1〜2週間ほど保存可能。
食べるときは冷蔵庫でゆっくり自然解凍すれば、ふんわり感が戻ります。
ただし、フルーツや生クリームの多いケーキは水分が抜けやすいので、冷凍には向きません。
ガトーショコラやチーズケーキ系がおすすめです。
なんでクリスマスにケーキを食べるの?
実は、クリスマスにケーキを食べるのは日本独自の文化なんです。
この習慣を広めたのは、あの「不二家」。
不二家の創業者・藤井林右衛門(ふじい りんえもん)さんが、1922年(大正11年)にイチゴのショートケーキを「クリスマスケーキ」として販売したのが始まりでした。
当時はケーキがとても高級なものでしたが、昭和40年代ごろから庶民の間にも広まり、「クリスマス=ケーキ」というイメージが完全に定着しました。
つまり、日本のクリスマスケーキ文化はお菓子メーカーの戦略によって生まれたというわけです。
とはいえ、赤と白のショートケーキが「雪」と「サンタクロース」を思わせる見た目だったこともあり、自然と日本人の感性に合ったのかもしれませんね。
海外のクリスマスは何を食べてるの?
クリスマスは本来、キリストの誕生を祝う宗教的な行事。
そのため、国によって食べるものや祝い方も大きく異なります。
アメリカ

アメリカでは、クリスマスにケーキではなくクッキーを食べるのが主流。
子どもたちはサンタさんのためにクッキーを焼き、ミルクと一緒に置いておきます。
食卓にはターキー(七面鳥)やマッシュドポテトなどが並び、家族全員でディナーを囲むのが伝統です。
日本のようにカップルで過ごすというより、家族のための日なんですね。
ドイツ

ドイツでは「シュトーレン(Stollen)」というお菓子を食べます。
酵母の入った生地に、レーズンとレモンピールやオレンジピール、それにナッツなどが練り込まれ、焼いた後の真っ白になるまで粉砂糖がまぶしてあるお菓子です。
ドイツでは、クリスマスの4週間前から少しずつ切り分けて食べるのが習慣です。
フルーツが入っているので、日が経つにつれ風味が生地に移っていく味の変化を楽しみながら、クリスマス当日を待つ習慣があります。
フランス

フランスでは「ビュッシュ・ド・ノエル(Bûche de Noël)」が定番。
フランス語でビュッシュは「丸太(木)」でノエルが「クリスマス」でクリスマスの木という意味です。

そこにフォークで波模様を付けて、丸太のように見せるためチョコの枝やホイップクリームなどでデコレーションしているお菓子です。
「家族の絆を象徴する薪」をイメージして作られており、見た目にも華やかです。
まとめ|クリスマスケーキは好きなタイミングで食べよう!
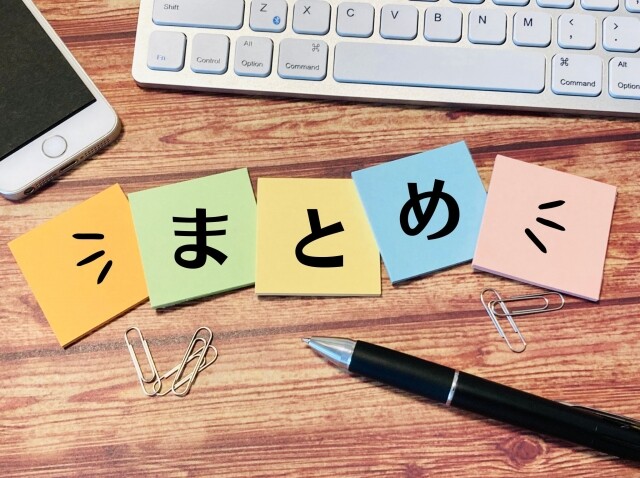
クリスマスケーキを食べるのは、12月24日の日没から25日の日没までの間が正解。
つまり、24日の夜に食べる人が多いのも納得ですよね。
また、食べきれないときは、
- 箱から出してラップをして冷蔵保存(1〜2日以内)
- 一切れずつ包んで冷凍すれば1〜2週間保存OK
という方法でおいしさをキープできます。
日本では不二家が広めた“ケーキを囲むクリスマス”ですが、それが今では冬の一大イベントになっています。
今年は、家族や大切な人と笑顔でクリスマスケーキを楽しんでくださいね。
【参考】