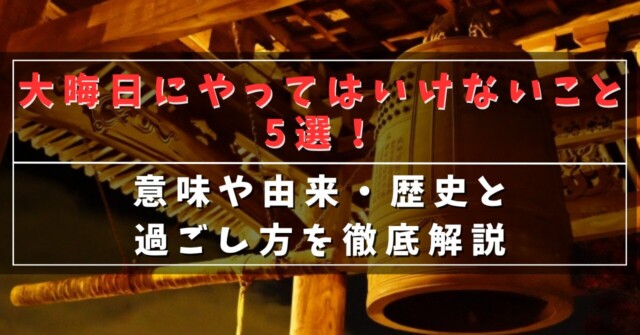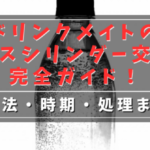大晦日は、一年の締めくくりとして多くの人が家を整え、新しい年を迎える準備をする大切な日です。
しかし、実は「やってはいけないこと」がいくつもあるのをご存じですか?
知らずに行うと「年神様(としがみさま)への失礼」とされるものもあり、古くからの日本の風習や信仰に根ざしています。
この記事では、大晦日にやってはいけないこと5選を中心に、その意味・由来・歴史、そして正しい過ごし方まで詳しく解説します。
大晦日にやってはいけないこと5選

大晦日は年神様を迎える“前夜祭”のような日。
そのため、古くから「神様を迎える準備が整っていない」「騒がしい行動をする」といった行為は避けるべきとされてきました。
ここでは、代表的な「5つのNG行動」とその理由を紹介します。
① 正月飾りを大晦日に飾る
大晦日に正月飾りを飾るのは縁起が悪いとされています。
本来、門松・しめ縄・鏡餅などは「年神様をお迎えするための目印」として12月28日までに飾るのが正式です。
29日は「二重苦(にじゅうく)」を連想させ、31日は「一夜飾り」といって、神様を迎えるのに準備不足とされてきました。
年神様への敬意を表すためにも、飾り付けは28日までに済ませるようにしましょう。
② 餅つきをする
大晦日の餅つきも、避けたほうがよいとされています。
餅は「年神様に供える神聖な食べ物」であり、大晦日に慌てて準備をすることは不敬にあたるとされてきました。
昔は28日までに餅をつくのが一般的で、31日に行うと「年神様への供物を前日に慌てて用意した」とみなされ、縁起が悪いといわれています。
③ 台所で長時間火を使う
大晦日は「火の神様(荒神様)」を休ませる日ともいわれています。
そのため、長時間火を使う料理や煮込み料理は控えるのが古来からの慣習。
特におせち料理は12月30日までに完成させるのが理想です。
大晦日は火の神様に感謝し、軽い調理や温め程度にとどめると良いでしょう。
④ 早く寝る
大晦日に早寝することも昔からタブーとされてきました。
「歳神様が家に来るのを迎えずに寝るのは失礼」と考えられていたのです。
地方によっては「早く寝ると白髪が増える」「シワが増える」などの俗信も残っています。
除夜の鐘を聞きながら、新年を静かに迎えるのが理想的な過ごし方です。
⑤ 掃き納め・大掃除
大晦日に本格的な掃除をするのもNGです。
掃除は年神様を家に迎える準備とされるため、31日に行うと「神様を追い出す」行為になると言われています。
大掃除は30日までに終え、大晦日は“軽く整える”程度にとどめましょう。
年神様を迎える家として、落ち着いた静けさを保つことが大切です。
大晦日の意味と由来・歴史
「大晦日(おおみそか)」とは、旧暦の12月の最終日を指します。
「晦日(みそか)」はもともと“月が隠れる日”という意味を持ち、月末を意味する言葉でした。
そこに「一年の最後の日」という意味を込めて“大晦日”と呼ぶようになったのです。
大晦日は、平安時代から「年神様を迎える準備をする特別な日」として大切にされてきました。
歳神様は新年の福や長寿を授けてくれる神様で、元旦に各家庭を訪れるとされています。
そのため、日本では昔からこの日に
- 家を清める
- お供えを整える
- 心を落ち着けて新年を待つ
といった行動が重視されてきました。
大晦日の伝統行事
大晦日には、古くから受け継がれてきた三つの行事があります。
どれも新しい年を迎えるために心と空間を整える大切な意味を持っています。
除夜の鐘(じょやのかね)
年の瀬を締めくくる音として親しまれているのが、全国の寺院で打たれる「除夜の鐘」です。
108回鳴らされる鐘の音には、人が持つ108の煩悩を一つずつ払い、新しい年を清らかな心で迎えるという意味があります。
多くの寺では31日の夜11時40分ごろから鐘をつき始め、年が明ける瞬間に最後の一打を響かせます。
寒さの厳しい夜ですが、除夜の鐘を聞きながら一年を振り返る時間は、何にも代えがたい静けさを感じさせてくれます。
晦日祓(みそかばらい)
「晦日祓」は関東地方を中心に行われる神事で、1年のけがれを祓い清めるためのものです。
神社では紙でできた人形(ひとがた)に息を吹きかけ、体をなでて穢れを移し、それを納めます。
年神様を迎える前に、心身ともに新たな気持ちで新年を迎えるための儀式です。
服装に決まりはありませんが、露出を控えた清潔な服装で臨むのが礼儀とされています。
二年参り(にねんまいり)
「二年参り」は、大晦日から元日にかけて神社や寺を参拝する行事で、年をまたいでお参りすることでご利益が倍になると伝えられています。
多くの人が除夜の鐘を聞いた後に神社へ向かい、旧年の感謝と新年の願いを込めて手を合わせます。
0時直後は混み合うため、深夜1時以降や元日の早朝に訪れると落ち着いて参拝できます。
参道では温かい甘酒やお守りが振る舞われることもあり、冬の夜にほっとする瞬間です。
大晦日の正しい過ごし方
大晦日は、一年の終わりを静かに締めくくり、年神様を迎えるための大切な一日です。
華やかなイベントもいいですが、本来の過ごし方を知ると、年越しの時間がより特別なものになります。
ここでは、古くから伝わる日本らしい大晦日の過ごし方を紹介します。
年越しそばで厄を断ち切る
大晦日といえば、やはり「年越しそば」。
細く長いそばは「長寿」や「家運の繁栄」を願う象徴とされ、同時に「一年の厄を断ち切る」意味も込められています。
食べるタイミングは年をまたがないうちに。
年を越してしまうと、厄を新年に持ち越すといわれるため、31日の夜のうちに食べ終えるのが習わしです。
地域によっては「にしんそば」(北海道)、「わんこそば」(岩手)など特色があり、家族の出身地や思い出の味を囲むのも素敵ですね。
年取り料理を囲んで感謝する
「年取り料理」とは、年神様を迎える前に家族でいただくお祝いの膳のこと。
おせちと似ていますが、年越し前に食べるのが特徴です。
鯛や紅白なます、昆布巻き、黒豆など、縁起の良い料理を並べ、一年を無事に過ごせた感謝を伝える時間とされてきました。
忙しい現代では、手作りにこだわらず、デパ地下や通販の年取りセットを取り入れるのも良い方法。
静かな年の瀬に家族が食卓を囲む光景こそ、昔から変わらない日本の美しい風景です。
おせちの準備と年の湯
おせち料理の準備は30日までに済ませ、大晦日は仕上げと盛り付けを中心に行います。
台所の神様を休ませる意味もあり、火を使うのは最小限に。
夜には「年の湯」に入りましょう。
これは、一年の汚れを落として新年を清めて迎えるための入浴です。
湯船にはゆずやヒノキを浮かべると香りも良く、心身ともにリセットできます。
入浴後は新しい下着やパジャマに着替え、清らかな気持ちで新年を待つのが古くからの風習です。
一年を振り返り、静かに迎える夜
テレビの特番を楽しむのもいいですが、照明を落として静かに過ごす時間もおすすめです。
家族で一年を振り返りながら、感謝の言葉を交わす。
カレンダーを新しいものに替え、部屋を整える。
そうした小さな行動が、気持ちの切り替えを助けてくれます。
やがて聞こえてくる除夜の鐘の音を背に、新しい年が穏やかであることを願いながら夜を過ごす――それこそが日本の「大晦日」の原点といえるでしょう。
まとめ|大晦日は「準備の日」ではなく「神様を迎える日」
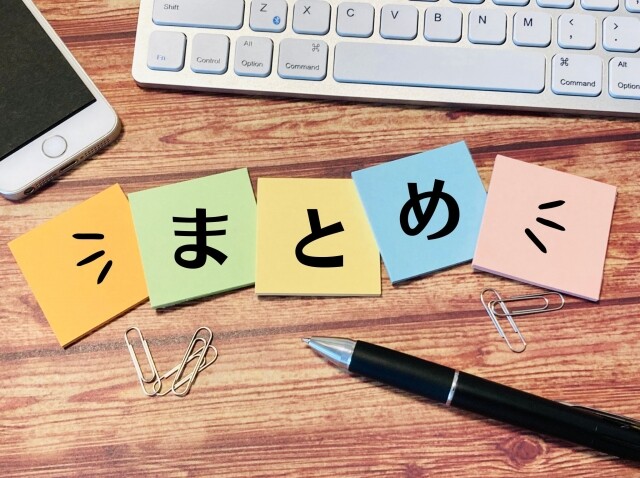
やってはいけないこと5選
- 正月飾りを大晦日に飾る
- 餅つきをする
- 台所で長時間火を使う
- 早く寝る
- 掃き納めをする
これらはいずれも、歳神様への敬意を欠かないための古くからのしきたりです。
現代では形式にこだわらない家庭も多いですが、意味を知ることで年越しがより特別な時間になります。
静かな夜に除夜の鐘を聞きながら、家族と一年を振り返り、新しい年の幸せを願いましょう。
大晦日は、神様とともに新年を迎えるための“祈りの日”なのです。
【参考】