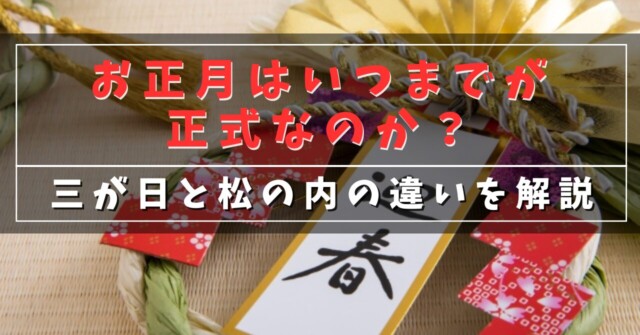お正月の区切りは「三が日」「松の内」「小正月」など、地域や習慣によって考え方が異なります。
一般的には1月3日までを指すことが多いですが、関東では1月7日、関西では1月15日までとする場合もあります。
この記事では、お正月はいつまでが正式なのかを整理しながら、三が日と松の内の違い、さらに過ごし方や関連行事についてもわかりやすく解説します。
お正月はいつまで?一般的な考え方

お正月の期間は「三が日」「松の内」「小正月」と複数の区切り方があり、日本の地域や家庭の習慣によって異なります。
ここではそれぞれの意味や特徴を詳しく見ていきましょう。
1. 三が日(1月1日〜3日)
「三が日」とは、お正月の最初の3日間を指します。
現代の日本では、この三が日をお正月の中心とする考え方が最も一般的です。
- 家庭行事の中心:元旦は家族で新年を祝い、おせち料理やお雑煮を囲みます。
親戚への挨拶回りも多く、この3日間を「年始のご挨拶期間」として大切にしている家庭も少なくありません。 - 社会的な習慣:官公庁や多くの企業も三が日を休業とし、初売りや福袋などの商業イベントもこの期間に集中します。
- 交通や旅行:帰省や旅行ラッシュも三が日がピークになるため、「お正月=三が日」という認識が広く根付いています。
2. 松の内(関東は1月7日まで、関西は1月15日まで)
「松の内」とは、門松やしめ飾りなどの正月飾りを飾っておく期間を指します。
この期間は「年神様」が家に滞在していると考えられており、お正月の延長線上に位置づけられます。
- 関東の松の内:一般的に1月7日までとされ、7日には「七草がゆ」を食べて無病息災を願う習慣があります。
この日を境に正月飾りを外す家庭が多いです。 - 関西の松の内:関西ではより長く、1月15日までを松の内とする地域が多いです。
このため、関西ではお正月気分がより長く続き、ゆったりと過ごす文化が残っています。 - 意味合い:松の内は年神様をお迎えする大切な期間とされるため、単なる「正月休み」以上の意味を持っています。
3. 小正月(1月15日まで)
「小正月(こしょうがつ)」は1月15日を中心とした行事のことで、「女正月」と呼ばれることもあります。
- 行事と風習:小正月には「どんど焼き」や「左義長」と呼ばれる行事が各地で行われ、正月飾りや書き初めを焚き上げて、一年の健康や安全を祈ります。
- 家庭での意味:かつては男性が年始の行事に忙しく働いた後、女性が休むことができる「女正月」として祝われることもありました。
現代ではこの習慣は薄れていますが、地域によっては今も行われています。 - お正月の締めくくり:小正月をもって正月行事の一区切りとする考え方があり、特に伝統を大切にする地域では「お正月は1月15日まで」とされています。
このように、お正月の期間は人によって「三が日まで」と考える場合もあれば、「松の内」や「小正月」までを含める場合もあります。
いずれも間違いではなく、地域性や家庭の習慣によって自然と違いが生まれているのです。
お正月の区切りが違う理由
お正月の区切りが「三が日」「松の内」「小正月」と複数あるのは、単に地域ごとの習慣の違いだけではなく、歴史や行事との関わりが深く影響しています。
ここではその理由を詳しく見ていきましょう。
1. 地域による習慣の違い
日本は古くから地域ごとに異なる文化を育んできました。
関東では1月7日を区切りとするのに対し、関西では1月15日までを正月とする地域が多いのはその一例です。
これは江戸時代に幕府が1月7日までを「松の内」としたことが関東に広まり、一方で関西には旧来の風習(15日まで)が残ったといわれています。
2. 歴史的な背景(旧暦との関係)
現在のカレンダーは新暦(太陽暦)ですが、明治時代以前は旧暦(太陰太陽暦)が使われていました。
旧暦では1月15日が満月の日にあたり、収穫祭や祈願祭が行われる特別な日でした。
そのため「小正月=正月の締めくくり」と考える文化が長く続いており、新暦に切り替わったあとも地域や家庭に根付いているのです。
3. 神社や寺院の行事との関わり
お正月は年神様を迎え、一年の豊穣や健康を祈る宗教的な意味を持っています。
神社や寺院では、1月7日や1月15日に合わせて祭礼や「どんど焼き」を行うため、その日を区切りとする考えが定着しました。
また、鏡開きの日(関東は1月11日、関西は1月15日)とも関連し、「行事の終わり=お正月の終わり」という認識にもつながっています。
お正月の区切りが異なるのは、歴史的な背景と地域文化の違いが重なっているからです。
「三が日」で区切るのは現代的でわかりやすい考え方ですが、松の内や小正月までを含めるのは古い習慣や宗教的行事を大切にした名残といえます。
どちらが正しいということではなく、それぞれの地域や家庭の習慣を尊重することが大切です。
お正月の過ごし方とマナー
お正月は、ただ休暇を楽しむだけでなく、古くから受け継がれてきた行事やマナーを守ることで、より意味のある時間になります。
とくに「飾りを外す時期」「年賀状の出し方」「初詣のタイミング」などは、多くの人が迷いやすいポイントです。
門松やしめ飾りを外すタイミング
正月飾りは年神様を迎えるための目印とされるため、外す時期にも決まりがあります。
関東では1月7日、関西では1月15日を目安に片付けるのが一般的です。
外した飾りは神社の「どんど焼き」でお焚き上げしてもらうのが望ましく、行事に参加できない場合は清めの塩をふってから処分するとよいとされています。
年賀状を出す目安
年賀状は松の内に届くようにするのがマナーです。
関東では7日まで、関西では15日までが目安とされます。
この期間を過ぎてしまった場合は「寒中見舞い」として出すのが正しい対応です。
遅れてでも一言添えることで、相手に対する礼儀が伝わります。
初詣はいつまでに行く?
初詣は三が日に済ませる人が多いですが、松の内までに参拝するのが一般的とされています。
ただし「必ずこの日まで」という決まりはなく、混雑を避けたい人は1月中や立春頃までに訪れても問題ありません。
重要なのは気持ちを込めて参拝することです。
食事や習慣にまつわるマナー
お正月の食卓には、おせちやお雑煮などの特別な料理が並びます。
おせちは三が日の間に食べ切るのが伝統とされ、7日には七草がゆをいただいて一年の無病息災を祈ります。
さらに11日(関西は15日)の鏡開きでは、供えた鏡餅を分けて食べることで力を授かるといわれています。
知っておきたい関連行事
お正月は三が日で終わりではなく、1月中にはさまざまな関連行事が続きます。
これらの行事は、年神様を送り、一年の健康や豊作を願うために古くから受け継がれてきました。現代でも多くの家庭や地域で大切にされています。
七草がゆ(1月7日)
1月7日に食べる「七草がゆ」は、無病息災を祈る習慣です。
おせちやごちそうで疲れた胃腸を休める意味もあり、食生活のリセットとしても親しまれています。
- 春の七草(セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ)を入れて炊く
- 関東ではこの日が「松の内の終わり」とされる
鏡開き(1月11日/関西は1月15日)
鏡餅を割って食べる行事で、年神様から力を分けてもらう意味があります。
家庭だけでなく、企業や道場でも鏡開きを行うことがあります。
- 関東:1月11日
- 関西:1月15日
小正月(1月15日)
1月15日を中心とする行事で、「女正月」と呼ばれることもあります。
この日には「どんど焼き」で正月飾りや書き初めを燃やし、炎にのせて年神様を送り出します。
- どんど焼き(左義長):正月飾りや書初めを焚き上げる
- 地域によっては「小豆粥」を食べる習慣もある
七草がゆ、鏡開き、小正月はいずれも「お正月の締めくくり」として大切な行事です。
これらを意識することで、ただの連休ではなく、心を込めて新しい一年を始めることができます。
まとめ|お正月は地域や習慣によって区切りが違う
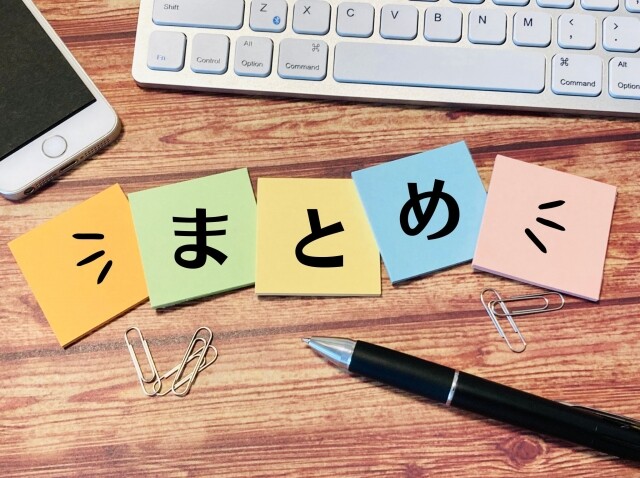
お正月は「三が日」「松の内」「小正月」といった複数の区切り方があり、地域や家庭によって考え方が異なります。
一般的には三が日で一区切りとする人が多いですが、関東では松の内の1月7日、関西では1月15日、小正月までとする場合もあります。
いずれも正解であり、どの区切りを選ぶかは地域の風習や家族の習慣に合わせて考えれば十分です。
また、七草がゆや鏡開き、どんど焼きといった関連行事を通じて、年神様を送り出し、無病息災を祈ることも大切な意味があります。
正しいマナーを意識して過ごすことで、新しい一年を清々しい気持ちで迎えることができるでしょう。
【参考】
⇒大晦日の食べ物ランキングTOP10!そば以外のおすすめや“縁起が悪い食べ物”も解説
⇒師走も佳境の意味とは?「近づき」「半ば」「かける」はいつを基準に言う?
⇒年賀状をやめる文例集!関係を崩さず伝えるコツと相手別の書き方