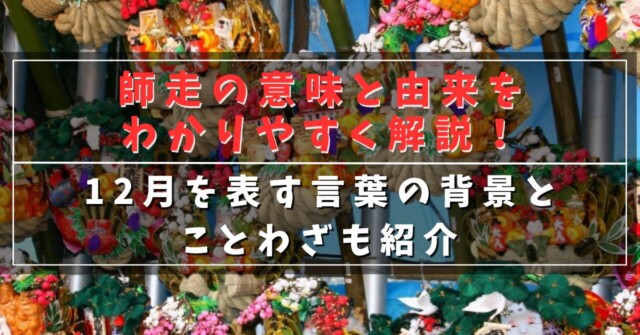年末が近づくと、テレビやニュースでよく耳にする「師走(しわす)」という言葉。
なんとなく“忙しい季節”のイメージがありますが、実は深い意味と長い歴史を持つ日本独特の言葉です。
この記事では、師走の本来の意味や由来、いつの時期を指すのか、さらに関連することわざまでわかりやすく紹介します。
読み終えるころには、「なぜ12月を師走と呼ぶのか」がすっきり理解できるはずです。
師走とは?意味と使われ方をやさしく解説

「師走(しわす)」とは、旧暦でいう12月を表す言葉です。
現代でもそのまま新暦の12月を指す季語として広く使われています。
年の瀬が迫り、仕事や行事で人々が慌ただしく動き回る――。
そんな年末の雰囲気を表す言葉として、「師走」という響きは今も親しまれています。
たとえば、「師走に入って気忙しくなった」「師走の街は活気がある」など、“年末の慌ただしさ”や“締めくくりの時期”を表すときによく使われます。
また、ビジネス文書や季節の挨拶でも「師走の候」「師走の折」など、12月を表す時候の挨拶として使われます。
師走の読み方
師走は一般的に「しわす」と読みます。
古くは「しはす」と発音されることもありました。
さらに、古文献の中では稀に「かんざつ」「ていし」といった読み方も登場しますが、現代ではあまり使われていません。
日常では「しわす」で問題ありません。
師走の由来は?有力な4つの説を紹介
師走の語源にはいくつかの説がありますが、主に次の4つが有名です。
中でも最も広く知られているのが「僧侶(師)が走る説」です。
① 僧侶(師)が走る説【最有力】
年の暮れは、仏教の法要「仏名会(ぶつみょうえ)」などが行われる時期。
お坊さん(師)が各家庭を回って読経を行うなど、非常に忙しく走り回る姿が見られました。
この様子から、「師が走る=師走」という言葉が生まれたと言われています。
つまり「師走」とは、師(僧侶)が東西を駆け巡るほど忙しい月という意味。
現代でも「先生や上司が走り回るほど慌ただしい時期」というニュアンスで使われるのは、この語源の名残です。
② 御師(おし・おんし)が忙しい説
御師とは、神社や寺院の参拝者を世話したり、宿泊を手配したりする人のこと。
昔は信仰の中心である伊勢神宮などで活動し、年末は特に忙しい時期でした。
そこから「御師の走る月=師走」と呼ばれるようになったという説です。
同様に、教師が年末で忙しいからという俗説もあります。
③ 当て字説(言葉の響きが先)
もともと12月のことを「しはす」と呼んでおり、後から当て字として「師走」という漢字をあてたとする説。
意味というよりも、響きの美しさを重視した古い表現だった可能性があります。
④ 年が果てる説(としはつ→しはす)
「年が果てる」=「としはつ」が転じて「しはす」となったという説もあります。
この場合の「師」は“終わり”を意味する古語「し」、「走」は“過ぎ去る”を表す「す」が由来とされています。
その他の説:借金を返す月?
地方によっては、12月は農家が一年の収穫を終え、借金を返すために走り回る時期だったという俗説もあります。
「師走=借金の清算月」という言い回しは、年末の慌ただしさを象徴するものとして語り継がれています。
師走はいつ?旧暦と新暦の違い
師走は旧暦(太陰暦)では12月下旬から翌年1月上旬ごろにあたります。
ただし現代では、新暦に合わせて12月1日から12月31日までを師走と呼ぶのが一般的です。
つまり「師走=12月」という認識で問題ありません。
年明け以降に使うことはなく、主に年末の挨拶や文章の中で使われます。
師走と同じく12月を表す言葉
日本語には、師走以外にも12月を表す美しい言葉があります。
- 極月(ごくげつ) … “一年の極み”という意味。年の終わりを象徴。
- 春待月(はるまちづき) … 新しい春を待つ月。希望を込めた表現。
- 歳暮(せいぼ) … 年の暮れ。贈答文化にも由来。
- 窮月(きゅうげつ) … 一年の終わりで“尽きる月”。
いずれも“年の締めくくり”を意味する雅な言葉で、時候の挨拶や和風デザインの文章にもよく使われます。
師走にまつわることわざ
日本では、師走をテーマにしたことわざも数多く残っています。
中でも代表的なのが以下の2つです。
「師走の空」
年末の慌ただしい時期を表す言葉で、「落ち着かないまま時間が過ぎる」という意味があります。
「百日の課すら師走の空」といえば、“百日分の仕事も師走の忙しさの中ではあっという間”というニュアンスになります。
「師走の名残りを惜しむも松の内」
年末の忙しさが過ぎても、正月の松の内(1月7日ごろ)まではその余韻が残る――という意味。
忙しさと寂しさが入り混じる日本の年末年始らしい表現です。
まとめ|「師走」は日本人の一年のリズムを映す言葉
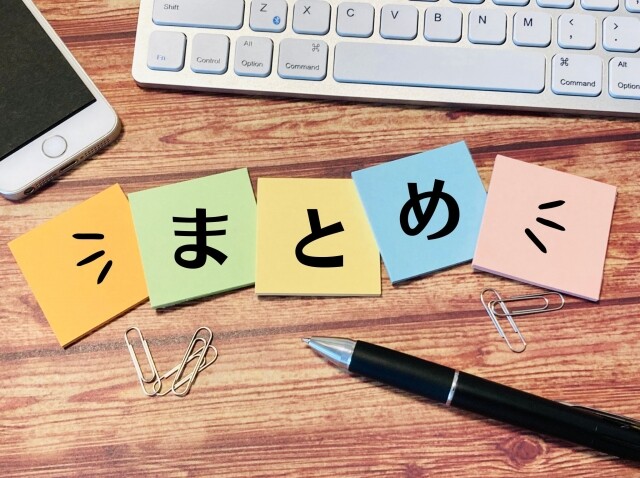
- 師走とは、旧暦12月を意味し、今では12月の別称として使われる
- 語源は「僧侶(師)が走る」説が最も有力
- 「御師が忙しい」「年果てる」など複数の説が存在
- 現代でも「師走の候」「師走の空」など、季節の挨拶やことわざに残っている
年末の空気を感じるたびに、「ああ、師走だな」と口にする日本人の感覚。
それは、単なる月の呼び名ではなく、一年を締めくくる心のリズムを表しているのかもしれません。
慌ただしさの中にも、どこか清々しさを感じながら――今年もまた、新しい年を迎える準備を始めましょう。
【参考】
⇒師走も佳境の意味とは?「近づき」「半ば」「かける」はいつを基準に言う?
⇒大晦日にやってはいけないこと5選!意味や由来・歴史と過ごし方を徹底解説