東北地方では、おせちを大晦日に食べる文化が今も受け継がれています。
一方で、関東や関西では元旦におせちを食べるのが一般的。
実はこの違いには、旧暦の風習や「年取り膳」と呼ばれる特別な文化が関係しているんです。
この記事では、東北地方のおせちを食べるタイミングの理由を中心に、九州・北海道・関西との違いをわかりやすく紹介します。
読み終えるころには、「どうして地域によって食べる日が違うのか」がしっかり理解できますよ。
東北地方はおせちはいつ食べる?

東北地方では、大晦日の夕方におせちを食べるのが一般的です。
多くの家庭では家族が集まり、年越し前にお祝いの食卓を囲みます。
その後、夜更けには年越しそばをいただき、新年を迎えるという流れです。
なぜ東北ではおせちを大晦日に食べるのかというと、そこには昔の暦と文化が深く関係しています。
旧暦では「日没後」が新年の始まりだった
現在のカレンダーでは、日付の切り替わりは深夜0時ですが、旧暦の時代では日没後が新しい一日の始まりでした。
つまり、日が沈んだ時点で新年を迎えたと考えられていたのです。
そのため、昔の人々にとって「大晦日の夜」はすでに新年。
「お正月を迎える」ことを祝うために、おせち料理を食べる風習が生まれたとされています。
「お正月を迎える」文化が残っている東北地方
東北地方では今でも、「お正月を迎える」こと自体を祝う風習が残っています。
これは「迎え正月」とも呼ばれ、年神様をお迎えするための神聖な行事です。
大晦日におせちを食べるのは、年神様への感謝とともに新しい一年の豊作や家族の無病息災を祈る意味が込められています。
その後に食べる年越しそばは、長寿を願うもの。
つまり、おせちと年越しそばを両方いただくことで、感謝と願いを両立させるという昔ながらの日本らしい習慣なのです。
九州地方はおせちはいつ食べる?
九州地方でも、一部地域(特に宮崎や鹿児島)では大晦日におせちを食べる文化が見られます。
東北と同じく、旧暦の風習が根強く残っているためです。
また、九州には「数え年」の考え方が今でも息づいており、大晦日を“みんなが一つ歳を取る日”と捉える地域もあります。
そのため、「おせち=誕生祝い」として食べる家庭もあるんですね。
子どもたちは「新しい歳を迎える日」として楽しみにし、親世代は「一年の感謝を込めて食べる」。
こうした温かい地域文化が、大晦日のおせちを支えているといえます。
北海道はおせちはいつ食べる?
北海道でも、大晦日におせちを食べる習慣が広く見られます。
この風習には「年取り膳(としとりぜん)」と呼ばれる行事食の文化が関係しています。
「年取り膳」としておせちを楽しむ
年取り膳とは、年神様に感謝し、新しい年を迎えるために食べる特別な料理のこと。
大晦日の夜に家族そろって食べることで、一年の締めくくりを行い、新たな年を迎える準備を整えます。
この「年取り膳」の中には、現在のおせち料理に通じる食材や意味が多く含まれています。
たとえば、昆布は「喜ぶ」、数の子は「子孫繁栄」、鮭は「生命力の象徴」。
こうした縁起物を家族みんなでいただきながら、新しい年の幸せを祈るのです。
北海道ならではの食材とおせち文化
北海道では、地域や家庭によって使う食材が少しずつ異なります。
代表的なのは、鮭やニシン、ハタハタ、鰊の昆布巻きなど。
海の幸に恵まれた土地らしく、塩気の効いたおせちが多いのが特徴です。
おせちを大晦日に食べながら家族が団らんし、日付が変わる頃に年越しそばを食べる――
そんな北海道らしい“ゆるやかな時間の流れ”が、いまも多くの家庭で受け継がれています。
関西はおせちはいつ食べる?
関西地方では、元旦におせちを食べるのが一般的です。
新しい年の始まりに、晴れやかな気持ちでお祝いの膳を囲むという考え方が根付いています。
関西ではおせち料理の味付けにも特徴があります。
出汁を活かした薄味仕立てで、素材の味を生かすのが関西流。
お雑煮には丸餅を使い、鯛やブリなど祝い魚を中心とした献立が多いのも特徴です。
一方の関東では、濃いめのしょうゆ味が好まれ、角餅を焼いてお雑煮に入れるのが主流。
同じおせちでも、地域によって味もスタイルもまったく違います。
このように、東北・北海道・九州では大晦日、関西や関東では元旦という違いが見られるのは、古い暦の解釈や地域文化の差が影響しているのです。
全国で異なるおせち文化の違い
おせちを食べるタイミングは地域ごとに異なりますが、どの地域でも共通しているのは「一年を感謝して迎える」という心。
現代では家族の予定に合わせて大晦日・元旦どちらにも食べる家庭も増えています。
地域別に見ると次のような傾向があります。
| 地域 | 食べる日 | 主な理由・背景 |
|---|---|---|
| 東北 | 大晦日 | 旧暦文化・迎える正月 |
| 北海道 | 大晦日 | 年取り膳の伝統 |
| 九州 | 大晦日(一部) | 数え年・誕生祝い |
| 関西・関東 | 元旦 | 新年を祝う文化 |
| 甲信越・四国 | 大晦日 | 地域差あり |
こうして見ると、「大晦日派」と「元旦派」に分かれているのがよく分かりますね。
FAQ(よくある質問)
Q1:東北では元旦におせちを食べないの?
A1:家庭によっては元旦にも少し残して食べる場合があります。
ですが、基本は大晦日に一度お祝いの席を設ける風習が強いです。
Q2:東北のおせちに特徴的な料理は?
A2:ニシンの昆布巻き、ハタハタの甘露煮、鮭の塩焼きなどが定番です。
甘味を控えめにした素朴な味わいが特徴です。
Q3:大晦日におせちを食べる他の地域は?
A3:北海道、九州の一部、甲信越地方などでも同様の風習が見られます。
いずれも旧暦文化の影響を強く受けています。
まとめ:東北地方のおせちは大晦日文化!全国の違いを楽しもう
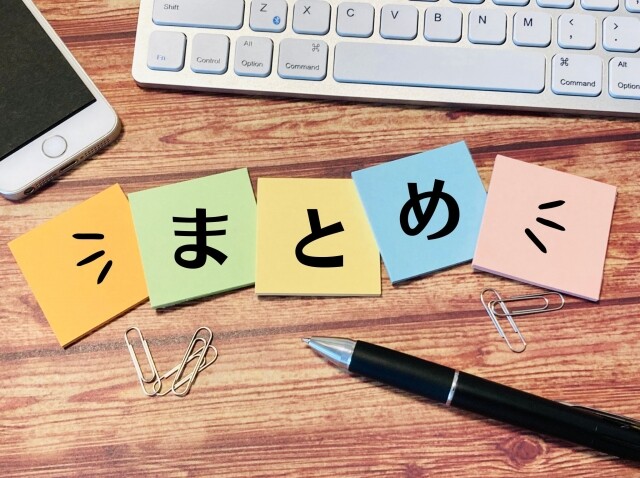
東北地方では、おせちを大晦日に食べる文化がしっかりと残っています。
その背景には、旧暦の考え方や「お正月を迎える」風習、そして「年取り膳」という伝統が深く関係しています。
一方で、関西や関東では元旦におせちを食べる家庭が多く、「新しい年を祝う」ことを重視しています。
つまり、東北は“迎える文化”、関西は“祝う文化”という違いがあるのです。
どちらも大切なのは、家族そろってお祝いの食卓を囲むこと。
年の瀬に食べるおせちにも、元旦に味わうおせちにも、それぞれの土地の温かさが込められています。
【参考】
⇒おせち福袋2026はいつから?販売スケジュールと人気ショップを総まとめ
⇒師走の意味と由来をわかりやすく解説!12月を表す言葉の背景とことわざも紹介



